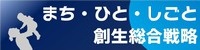国民年金について
国民年金とは
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになります。
国民年金の加入
| 種別 | 対象 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | 農林漁業者、自営業者、学生、無職など (第2号・第3号被保険者を除くすべての人) |
| 第2号被保険者 | 会社や公務員の人で厚生年金や共済組合に加入している人 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
- 第1号、第2号、3号被保険者まで、すべて強制加入です。
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。- 年金額を増やしたい方は65歳までの間
- 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
- 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
国民年金に関する届出
加入・喪失について
20歳になったときの加入は、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせが届きますので手続きは不要ですが、以下の場合は届出が必要となります。
| こんなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 会社を退職したとき (第2号→第1号被保険者) |
|
| 会社員の配偶者の扶養から抜けたとき (第3号→第1号被保険者) |
|
| 死亡したとき |
|
- 会社に勤めるなどして厚生年金・共済年金に加入する場合や、加入している配偶者の扶養に入る場合には事業所を経由して手続きがありますので届出は不要です。
その他の届出
| こんなとき | 申請先 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 保険料の口座振替を希望するとき | 金融機関、役場、または年金事務所 |
|
| 保険料のクレジットカード納付を希望するとき | 役場または年金事務所 |
|
| 保険料の免除・納付猶予を希望するとき | 役場または年金事務所 |
|
国民年金保険料の納付について
納付方法
国民年金保険料は以下の方法で納入することができます。
- 納付書を使用する
- 口座振替
- クレジットカード
- 電子決済
- 口座振替、クレジットカード納付については役場でも申請することができます。
それぞれの納付方法についての詳細は下記をご覧ください。
・国民年金保険料の納付方法について(外部サイト)
保険料の前納
国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて支払う(前納)ことができ、納付期間や方法により割引が受けられ大変お得です。
納付方法、前納する期間等により割引額が異なりますので詳細は下記をご覧ください。
・国民年金保険料の前納について(外部サイト)
国民年金保険料の免除・納付猶予
経済的な理由や失業などで保険料の納付が困難な人は、保険料が免除・猶予される制度があります。申請のあった月の2年2ヶ月前までの期間(保険料の納付期限から2年を経過した期間を除く)についてさかのぼって申請することができます。
免除・納付猶予申請のメリット
- 納付免除・猶予を受けた期間中にケガや病気で障害や死亡といった事態が発生した場合にも、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができます。
- 納付免除を受けた期間であっても老齢基礎年金受給の際に一部を受け取ることができます。また、10年以内であればさかのぼって保険料を納付(追納)でき、将来の年金額に反映することができます。
- 納付猶予を受けた期間については老齢基礎年金額に反映されませんが、追納することにより将来の年金額に反映することができます。
学生納付特例制度
学生本人の所得が一定以下の場合、在学中の保険料を後払いすることができる制度です。なお、学生納付特例承認後、10年以内であれば、追納をすることができます。3年目以降に追納する場合は、一定率を乗じた金額が加算されますので、ご注意ください。ただし、特例を受けた期間は、老齢年金を受けるための資格期間には含まれますが、追納をしないと受け取る年金額の計算には算入されません。
産前産後期間の保険料免除
出産予定月の前月(多胎妊娠の場合には出産予定月の前4ヶ月)から出産予定月の翌々月までの各月分の保険料の納付が全額免除されます。
この場合の出産というのは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩のことで、早産、死産、流産および人工妊娠中絶を含み、この産前産後免除期間の各月は、保険料納付済期間に算入されます。
届出は、出産予定日の6ヶ月前から行うことができ、期限も設けられていませんが、早めの届出をお勧めします。
国民年金給付の種類
国民年金給付には以下の種類があります。これらを受け取るためには「裁定請求」という手続きをすることになっております。申請先は種類と加入年金により異なりますので詳細は下記リンクをご覧いただくか、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)までお問い合わせください。
・年金の受給に関する届出・手続き(外部サイト)
障害基礎年金
被保険者が65歳前に障害等級表1・2級に該当する障害者になったときに支給されます。ただし、初診日前の加入期間のうち、保険料を滞納した期間が3分の1以上ないことが必要です。また、20歳以前に障害者になった人についても、20歳に達したときから支給されます。
遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子(※)がある配偶者」または「子」に支給されます。
※子とは18歳到達年度末(障害のある場合は20歳未満)までを指します
寡婦年金
老齢基礎年金を受けるための条件を満たした夫が、障害基礎年金・老齢基礎年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳までの5年間支給されます。
死亡一時金
3年以上保険料を納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金も受けないで死亡したとき、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹)に遺族基礎年金が支給されない場合に支給されます。
※支給額は保険料を納めた期間に応じて異なります
年金生活者支援給付金制度
公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
制度など詳しく知りたい場合は下記までお問い合わせください。
給付金専用ダイヤル
電話番号:0570-05-4092
石巻年金事務所
電話番号:0225-22-5115
離婚時の年金分割制度
離婚した場合、二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、お近くの年金事務所までご相談ください。